眺めて、動いて、読んで
2025年5月17日㈯、ダブリン・ラボの今年3回目のワークショップでした。
今回のテーマは、落語。「なりきり『文七元結』」ということで、人情噺の傑作を複数の視点からひも解く企画でした。
ファシリテーターは、阿部路子さん。私と長いこと、「古典落語の読み合わせ遊び」をやってきたパートナーです。
今回、二人の落語遊びを拡大して、ダブリン・ラボで展開してみることになりました。
今回は、いつもの調布を飛び出して、国立の「ギャラリー・ビブリオ」さんにて開催。
こちらは古民家を活かした画廊なのですが、貸会議室も併設されています。
今回、江戸の世界観を体感するためにも、趣のある和室の会議室「富士の間」をお借りしました。
お部屋には大きな富士山の風景画がかかっています。
うかがうと、銭湯ペンキ絵師・丸山清人さんの作品だとのこと。ギャラリー・ビブリオさんでの個展の際に、ライブペインティングで書いていただいたものだとか。
趣深い部屋で、総勢7名でにぎやかに活動しました。
「なりきり」ということで、まずは各自が落語家さんになりきり、落語家としての名前やその由来などを自己紹介代わりに発表。
皆さんそれぞれに、思い入れのある名前がつきました。
その後、喜多川歌麿の「大名屋敷の大晦日(大掃除)」の絵を見ながら、絵をまねてポーズするワーク。
阿部さんによると、この絵は大名屋敷とは言っているものの、遊郭の様子から歌麿が想像して大名屋敷を描いた絵であるらしいとのこと(調べてくださいました)。
「おそらく遊郭の大晦日も、こんな感じでバタバタ大掃除していたに違いない」ということで、絵の登場人物になりきってみることに。
「文七元結」の主人公、長兵衛さんもめくっていたであろう花札を使ってペアを決め、まねる絵を決めて、実際に体を動かしてみます。
「何をやってるのかな?」「どんな話をしているのかな?」など、対話しながらポーズを決めていきます。

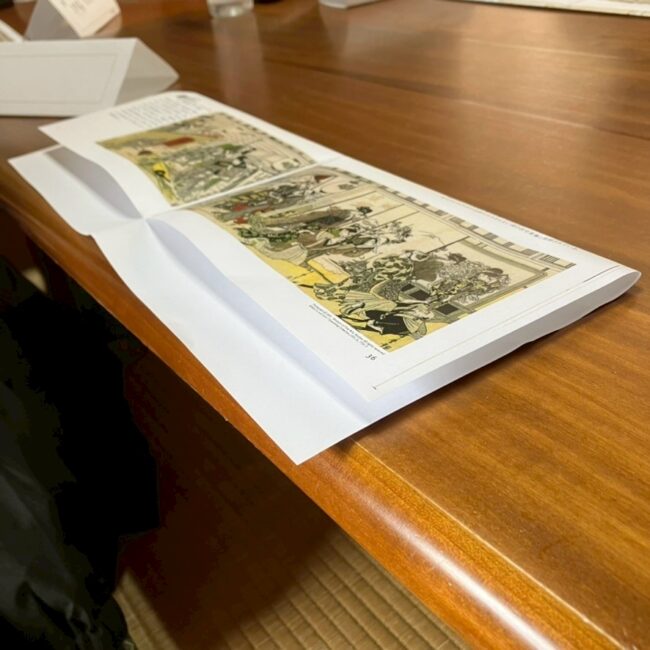
「選ぶ部分が被っちゃうかな?」と思いきや、それぞれのペアが全部違う部分をチョイス。
できたポーズを見ながら、もっと似せるにはどんな姿勢や目線にしたらいいか」など調整しながら、完成!
実際に語り合いながらポーズをとることで、歌麿の浮世絵の世界にみんなが入り込めたような気がしました。
その後は、ペアを変えて、いよいよ「文七元結」の読み合わせです。
長い噺なので、「佐野槌の内証(女将の部屋:女将と長兵衛の会話)」と「吾妻橋(長兵衛と文七の会話)」を抜き出しました。
「佐野槌の内証」では、女将役と長兵衛役を分けて読んでみました。女将、やけに妖艶だったり、諭すように話すタイプだったり、静かな中にも迫力満点だったりと、三者三様で面白かったです。
長兵衛も、私は結構軽薄な感じで読んじゃいましたが、お久に向き合って泣くシーンを、ゆっくりと心に染み入るように読んだ方もいて、とてもよかったです。

「吾妻橋」は、私が文七、阿部さんがト書き、その他の方が長兵衛で、長兵衛は句点でリレー読みにしました。前の方が作った流れに乗りながら自分のセリフを読むという、少し高度な取り組みです。
1回読んでだいたい様子をつかんでもらえたので、もう一度やってみました。2回目となると感情が乗り、臨場感のある読みができたかなと思います。


楽しくて、まったりの中にも程よい緊張感があって、あっという間の2時間15分でした。
また落語をもとにしたワークショップ、やってみたいと思います。




